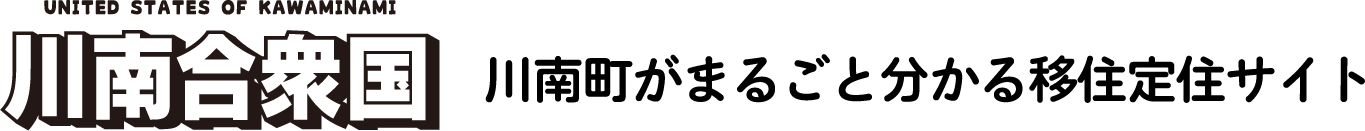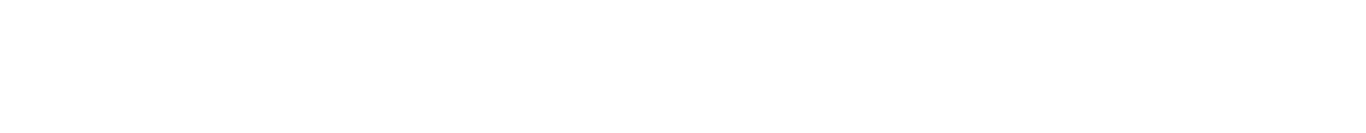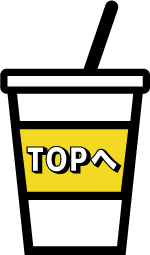涙と感謝の10日間

こんにちは。川南町地域おこし協力隊の塚井です。
先日、「関係人口創出に向けて ― 協力隊として最後にして最大の取り組み ―」というタイトルでブログを公開しました。
今回の記事は、その続編であり、開催のご報告になります。
初めてこちらの記事からご覧になる方は、ぜひ前回の記事「関係人口創出に向けて ― 協力隊として最後にして最大の取り組み ―」も併せてお読みいただけると嬉しいです。
(ページ下部にリンクを貼っています)
川南町コース第1期を終えて
2025年夏、9泊10日の「村おこしボランティア」川南町コース第一回目が幕を閉じました。
私は世話人のサポート役として、約1年前から企画を始め、やり方を考えたり、世話人を見つけること、宿泊拠点を見つけること、拠点施設の清掃・準備、運営体制の立案、そして受け入れの現場まで関わりました。
この10日間を振り返ると、参加者が町の方々と心を通わせ、暮らしや自然、文化に触れながら川南町を深く知っていく過程を間近で見届けられたことが、何よりも嬉しかった―。特に、世話人の御三方が学生との出会いを通じて日常に新しい風を感じ、「寂しい」と口にしてくれた瞬間。その言葉は別れの寂しさであると同時に、濃密な時間を過ごした証だと感じ、
私としては、そんな感情が生まれる場を作ることができたということに大きな達成感を感じました。
これまで自分にできることを、諦めずにやってきてよかったと、心から思いました。
この10日間は、参加者と受け入れ側、
互いの人生に刻まれる経験であり、ここに関わる全ての人にとって忘れがたい、かけがえのない時間となりました。
最終日から一週間ほどたった今でもまだ、余韻があります。
本当は、言葉にできないほど、言葉にするのが惜しいほどの感情があるのですが、
ここではやはり協力隊の活動報告も兼ねて、世話人サポートの私の視点ではありますが、この10日間を私なりの視点でまとめたいと思います
町の名前も知らなかった学生たち
参加者5名は、川南町という地名すら知らない、普通の大学生。
縁もゆかりもない土地に降り立ち、少し緊張した面持ちだった彼らが、農作業や地域行事、町内ドライブを重ねるうちに、少しずつ表情を和らげていく姿が印象的でした。
最初は、「宮崎県に初めてきました!」と言っていた参加者でしたが、
10日間を共に過ごす中で、「人が温かい町だ」「食べ物がおいしい」「自然を満喫できた」といった言葉が自然と出てくるようになりました。
最初は「宮崎県」という大きな枠組みで話していた参加者も、いつしか「川南町は…」と町の名前を自然に口にするようになっていることに気づきました。その変化からは、川南町を思う気持ちが芽生えてきたことを感じます。
移住担当者として、都市部やオンラインで移住相談を行ってきましたが、
町のことをどんなに丁寧に説明しても、どんなに広告を工夫しても、やはり実際に町を訪れ、自分の目で見て体験することには及ばないと感じました。
NPO法人ECOFFの村おこしボランティアは、北海道から沖縄まで多様なコースがあります。その多くは小さな離島ですが、川南町のような里山地域もあります。
川南町コースの意義は、特別感のある観光地ではない場所で、「リアルな暮らし」を体験できることにあると考えています。必要なインフラやお店は整っている一方、人口やなりわいは減少し、地域の衰退が進む――これが地方の“ありのまま”の姿です。
また、川南町は農業の町であり、日々の暮らしに欠かせない食料の生産地でもあります。ここで育つのは、南国らしい作物だけでなく、お米やピーマン、サツマイモといった、普段の食卓に並ぶ身近な作物です。特別感のある作物ではないからこそ、暮らしに直結する農業の“リアル”を感じられるのだと思います。
そしてこのボランティアでは、収穫だけでなく、定植や苗の管理といった地道な作業にも携わります。必ずしも楽しいことばかりではなく、時には大変だと感じることもあるでしょう。しかし、そうした過程を含めてこそ、この土地ならではの本物の体験になると考えています。
私も何度か現場に足を運びましたが、彼らが農業について、地域について触れる姿を見ると、川南町では当たり前の景色や体験が、彼らにとっては新鮮で、大きな学びになっているんだなぁと感じました。
今回参加してくれた5名の参加者は、この川南町コースで、この地域に息づく「リアルな暮らし」をしっかりと体験してくれたのではないかと思います。

背中で語る大人たちと情緒的な学び 住民主体だからこそできたこと
この活動の中で印象的だったのは、世話人や協力者たちの存在感です。
世話人方は特別な演出をするわけではなく、日々の暮らしをそのまま見せながら参加者と関わっている様子がありました。
その背中からは、仕事に向き合う姿勢や暮らしの中にある価値観が自然と伝わっていたのではないかと思います。
ときには冗談を交え、ときには真剣な助言をし、参加者の心に残る言葉をかけてくれる―。
参加者は、そのやり取りの中で自分の将来や生き方を考えるヒントを得たと言っていました。
この村おこしボランティアは、自治体主体でも協力隊主体でもなく、真の「住民主体」のプロジェクトです。
私は発起人として準備に関わりましたが、世話人として現場を回したのは町民チームです。
もともと知り合い同士だったメンバーもいましたが、今回の受け入れを通して、日を追うごとにチームワークが磨かれていったように感じます。
受け入れ側も「ボランティア」です。稼業の合間を縫いながら参加者との時間を作ってくださり、明日の天気や農作業の進捗を踏まえ、毎日のように話し合いを重ねた激動の10日間でした。そこからは、全員が温かく参加者を迎え入れようという想いが伝わってきました。
忙しい中でもお互いに支え合い、「参加者のために」という思いを自然と共有できたことが、大きな力になったのだと思います。
この関係性は参加者にも伝わり、「世話人や協力者の関係性」から川南町の人の温かさをを感じ取ってくれた参加者もいました。
こうした情緒的なつながりは数値では測れませんが、確かに深く残るものだと思います。
最終日、「5人でまた川南町に帰ってきたい」と声を揃えてくれたこと。
10日間を通して様々な体験と人との出会いから生まれた言葉こそが、本物の「良さ」である証拠です。
町の人と過ごす時間の積み重ねが、参加者にとっても、受け入れる側にとっても、どれだけかけがえのない時間となっていたかは計り知れません。
住民自身が自主的に動き、地域の魅力を外から来た人と共有する――これは行政主体のイベントでは生み出しにくい価値であり、今後町の誇りとなっていくのだと思います。

続けることの意味とこれから 関係者の皆様へ
この取り組みは単発のイベントではなく、今後大学生の夏休みと春休みごとに継続していくことを目指しています。
参加者の累計が5人、10人、20人…と、川南町を「第二の故郷」のように感じてくれる若い方が少しずつ増えていく未来を描いているのです。
だからこそこれは、町民が世話人として指揮を執る形をとっています。(詳細は前回の記事「関係人口創出に向けて ― 協力隊として最後にして最大の取り組み ―」で紹介しています。)
ですが、 参加者が川南町を第二の故郷のように思ってくれたとて、移住や定住といった目に見える成果が出るのは時間がかかるだろうし、 なによりこの10日間で築き上げた情緒的なつながりは数値化できません。
しかし、この期間に関わった世話人や協力者、参加者の方々は、おそらく“結果”よりも「楽しかった」「心が熱くなった」「いい思い出になった」という気持ちを大切にしているかと。私自身も、そう思っていただけるなら、それで十分です。
それでも、関わった人の心に残る経験は確実に地域を変えていくと、私は信じています。
この村おこしボランティアに世話人として関わることを決心してくださった3名の方々、協力者の皆さんは、本当に大きなことを引き受けてくださいました。私が偉そうに言える立場ではないのですが、町にとって誇り高いことだと私は思います。
地域おこし協力隊として、1年目から少しずつ人脈を築きながら皆さんにたどり着きました。
村おこしボランティアに関わるのが皆さんで本当によかった。出会えて本当に良かった。
私は皆さんのことが、大好きです。幸せです。
しかしながら、村おこしボランティアの受け入れはここで終わりではありません。むしろ始まったばかりです。
川南町と、ここで出会った人たちと、この挑戦を、もっと面白くしていきたい。これからも、どうかよろしくお願いします。