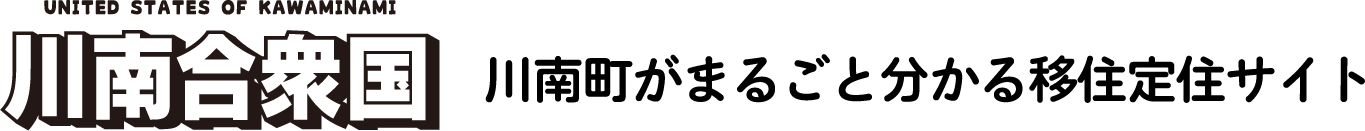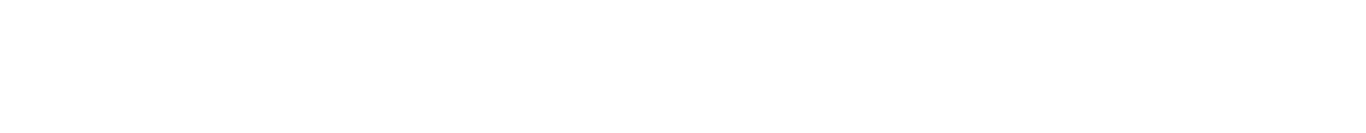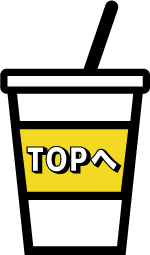関係人口創出にむけて ー協力隊として最後にして最大の取り組みー

こんにちは。川南町地域おこし協力隊の塚井です。
今回は、私にとって協力隊としての最後で、そして最大の取り組みとなる事業についてご紹介します!
突然ですが、「関係人口」という言葉を聞いたことはありますか?移住でも観光でもないけれど、地域と継続的につながってくれる“第三の関わり方”として、今とても注目されています。
私は、川南町で移住・定住促進を担当する地域おこし協力隊として活動しており、移住希望者のサポートに加えて、「関係人口を増やすこと」にも力を入れています。
「地域に人を呼ぶ」と聞くと、まず“移住者”の確保をイメージされる方が多いかもしれません。
でも、実際にはいきなり移住を決める人はごくわずか。だからこそ、「いきなり移住」ではなく、「まず関わる」というステップをつくることが、とても大切だと考えています。
昨年の夏に開催した「看護×田舎暮らし~おためし地域体験プログラム~」も関係人口創出に向けて取り組んだ事業でした。しかし、一向に応募者が集まらかったという結果から、協力隊としてあるいは一つの町が単独で、多くの若者の興味を引き、応募者を集めるのはとても難しいことであると痛感しました。この事業を同じ形で継続していくことは困難であると感じました。
やはり、ある程度の集客を望むためには、すでに全国的な認知度やネットワークを持つ団体と連携することが必要であると考えました。
そんな想いから、今回ご紹介するのが、NPO法人ECOFF(エコフ)さんと連携して行っている「村おこしボランティア」という取り組みです。全国から集まった若者たちが、9泊10日のあいだ地域に滞在し、農業を中心に地域のさまざまな困りごとを一緒に解決するボランティア活動です。
実はこの企画、昨年の夏から少しずつ構想を練り、1年ほどかけて準備してきたものです。
今回は、その背景やこれまでの取り組み、そして現時点でのご報告をお届けしたいと思います。
村おこしボランティアとは?
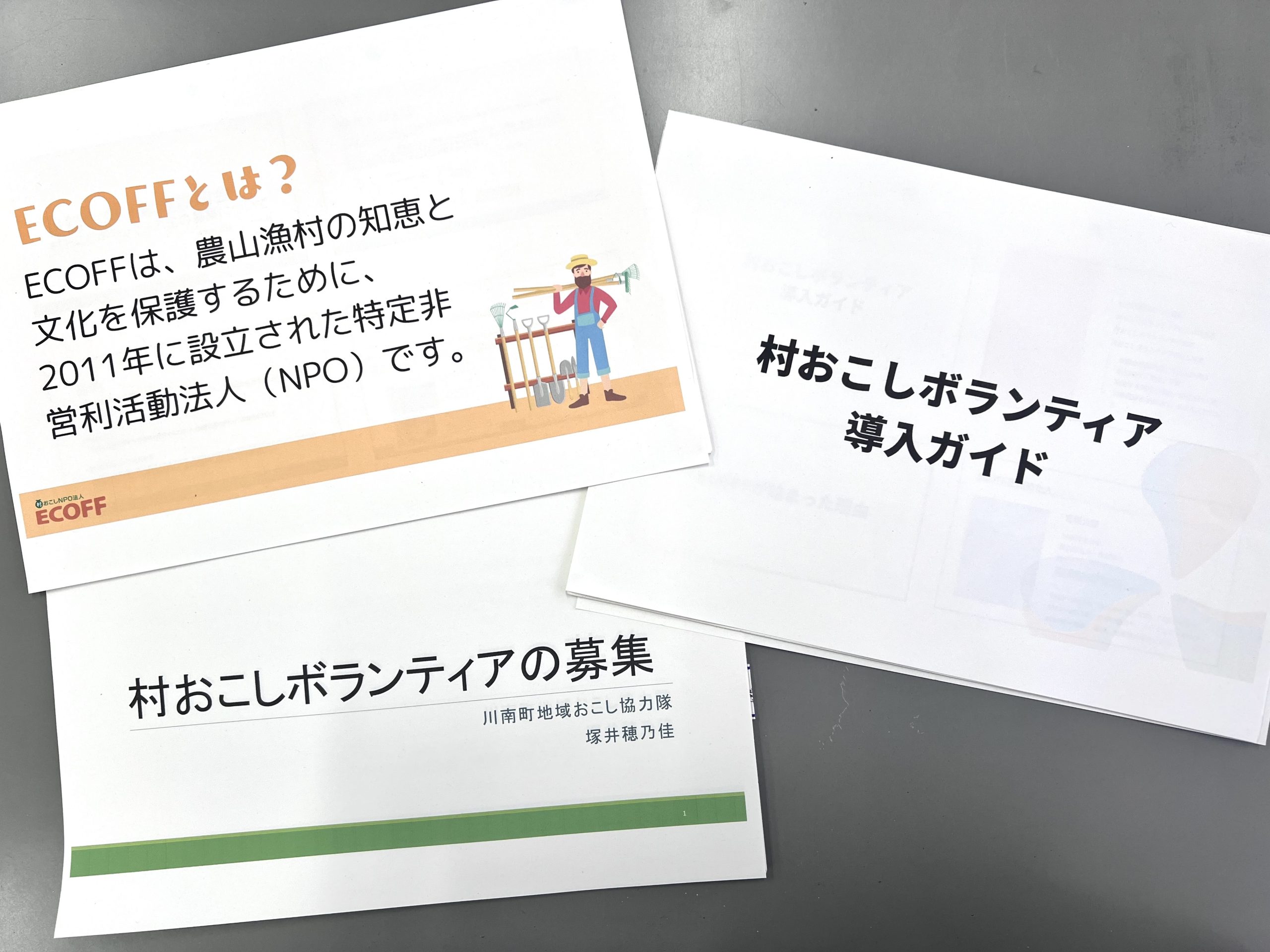
今回取り組んでいる「村おこしボランティア」は、NPO法人ECOFF(以下、「ECOFF」)と連携して実施している事業です。
ECOFFは、「都市と田舎をつなぐ」をテーマに、全国の離島や農山漁村で地域活性化に取り組んでいる団体です。住み込み型のボランティアプログラムをはじめ、地域産品の販売支援や観光資源の活用など、地域の課題に合わせた多様な活動を展開しています。
その中でも「村おこしボランティア」は、地域の人手不足や過疎化といった課題に対し、全国の若者たちが現地に滞在しながら関わるという、滞在型のボランティアプログラムです。北海道から沖縄まで、さまざまな地域で実施されており、毎年、大学生の長期休みに合わせた「夏日程」と「冬日程」の2期にわたって、それぞれの地域で募集を開始します。滞在期間は基本的に「9泊10日」で参加者同士の共同生活とボランティア活動を通して、地域とのつながりを育むことを目的としています。
参加者は、地域づくりや田舎暮らしに関心のある大学生が中心で、関東・関西の都市部出身の参加者も多いです。滞在中は、地元の農業やイベント運営の手伝いなどに加え、地域の方々と直接ふれあう交流の時間も多く設けられています。
実は、私も大学生の時に、一度与論島コースに応募し(台風により中止になり行けていませんが…)、社会人1年目で一度、江田島コースに参加をしたことがあります。
このプログラムでは、ただ作業をこなすのではなく、人との出会いや地域の暮らしに触れることを大切にしている点が大きな特徴です。アルバイトではなく、賃金の発生しない“ボランティア”として関わるからこそ、利害を超えた自然な関係が生まれ、心のこもった交流が育まれていきます。
さらに、このプログラムには欠かせない存在がいます。それが「世話人」と呼ばれる、地域の案内人です。
世話人は、参加者の現地での案内や生活サポート、活動先との調整などを担い、地域と参加者をつなぐ“橋渡し役”として重要な役割を果たしています。
そして、もう一つ特筆すべき点は、参加者も世話人も、どちらもボランティアとして関わっているということ。
お金ではなく、人と人との信頼や思いによって成り立っているからこそ、作業の合間に交わす会話や、ふとした日常のやりとりが、地域を知るかけがえのない時間へと変わっていきます。
私が着手したのはこの村おこしボランティアを川南町で実施すること、「川南町コース」を立ち上げることでした。それが、令和6年7月中旬のことでした。
ゼロから1へ

それから、ECOFFの代表の方に連絡をとり、ときに町の職員にも力を貸していただきながら協議を重ねてきました。
当初、私自身が世話人を務める方向で考えていましたが、協議を重ねる中で、ある課題に気づきました。
地域おこし協力隊には、最大3年間という任期があります。私自身も、任期後は県内での就職を予定しています。その中で、世話人が任期を機に不在になってしまうと川南町コースは終わってしまう。継続性がなければ一度きりで終わってしまう、ということに課題があると感じました。
関係人口の創出において本当に大切なのは、毎年少しずつでも人が地域と関わり続けられる仕組みをつくること。 どんなに素晴らしい取り組みでも、一過性で終わってしまっては意味がありません。だからこそECOFFのプログラムでは夏日程と冬日程で定期的に募集をかけ、数人でも地域に人を呼び込む仕組みがあるのです。
この点については、ECOFFの担当者の方からも繰り返しアドバイスを受けていました。実際、全国の村おこしボランティアの受け入れ先を見ても、任期や異動がある「自治体職員」が世話人を担っている例はほとんどなく、どこも地域の住民が主体的に動いているとのことでした。
だったら、私がやるべきことは「自分が世話人になること」ではなく、
「この町の中から、世話人として共に関わってくれる人を探し出すこと」ではないか。私はそう考えました。
このことは一見、無責任に聞こえるかもしれません。
しかし、持続可能な取り組みにするためには、地域の人自身が興味を持ち、納得して関わってくれることが何より大切であることに気づきました。
そして、その“住民の主体性”を育てていくことこそが、地域おこしの本質なのではないか——そう思い、私は町の中で世話人になってくれる人を探すことから始めました。
まずは、これまで協力隊として関わらせていただいた方にアポを取り、一人ずつお話しに行きました。
ここで大切にしたのは、「お願いする」のではなく、「提案する」という姿勢でした。
無理に頼むのでは意味がないし、そうして始まったものは続きません。大事なのは、その人の中にある“何かやってみたい”という気持ちがあるかどうかです。
とはいえ、「関係人口」も「村おこしボランティア」も、言葉すら聞き慣れないもの。何度も何度も説明し、思いを伝えました。話し下手な私は、時に言葉に詰まりながらも、ゼロを一にするために行動しました。
そんな中、ある方が、私の話を一通り聞いたあと、ぽつりと、
「やろうか」と一言、言ってくださったのです。
あまりにもあっさりとしたその一言に、私は思わず「本当ですか?」と聞き返してしまいました。
その方は、「おもしろそうだ」と言ってくださったのです。そして、「一人じゃ無理だから、誰か一緒にやってくれる人がいた方がいいよ」と、仲間になってくれそうな方を紹介してくれました。私はすぐにその方々にも話をしに行きました。
すると、不思議なくらい自然に、他2名の方にも興味を持っていただき、世話人が3名体制でスタートすることになったのです。これが令和7年1月末~2月上旬頃のことでした。
この御三方がいてくれなければ、川南町での村おこしボランティアは始まりませんでした。
本当に、心から、感謝しています。
続いての課題「宿泊所探し」
世話人が決まってからは、私の地域おこし協力隊としての残りの任期の中で、少しでもこの取り組みが継続できるよう、“土台づくり”に全力を注ぐことにしました。
運用体制の構築、募集ページの作成補助、活動内容の整理など、世話人と力を合わせて少しずつ形を整えていきました。
そんな中、最初に大きな壁となったのが、「宿泊場所」の確保でした。
NPOの性質上、参加者から宿泊費を徴収することはできません。そのため、町内で「無料で宿泊できる場所」を探す必要がありました。
公民館、ゲストハウス、民宿…。知人に声をかけたり、町内の施設に相談に行ったり、あらゆる可能性を探りました。
しかし、金銭面や受け入れ環境の問題もあって、なかなか条件に合う場所が見つからず、「せっかく世話人が決まったのに、受け入れができないかもしれない…」と焦りと不安に襲われていました。
そんな時、ある公民館の館長さんに相談をした際、「磯での体験を取り入れてみたらどう?」というアイデアをいただきました。
本来なら宿泊場所が決まってから活動内容を詰めるべきかもしれません。けれど、川南町でできる体験のストックを増やしておくのも無駄ではないと思い、まずは自分で体験してみようと、町の磯へ足を運びました。
ルールの範囲で海藻や貝を採らせてもらい、自然と触れ合ううちに、ふと、近くにいた公民館の集まりの方々とお話をする機会がありました。
村おこしボランティアのこと、参加者の宿泊先がまだ決まっていないこと——。
その話をすると、そこにいた方の一人が、
「今、実家が空いてるんだけど、良ければ見に来る?」と声をかけてくださったのです。
その方について行くと、案内されたのは、広々とした和室と縁側がある、とても温かな空間が残る空き家でした。
簡単に事業の説明をすると、「ぜひ使ってください」と、迷いのない優しい一言をいただきました。
思いがけない出会いとご厚意によって、止まりかけていた取り組みに光が差し込んだ瞬間でした。
これが令和7年3月末、そこからは、物事が一気に動き出しました。
空き家を使用するための取り決めやルールを整え、所有者のご家族への挨拶も済ませ、「いよいよ、ここを受け入れの拠点にしよう」と、世話人と一緒に掃除や片付けに取りかかりました。
本業の合間を縫って集まってくれた世話人、地域の協力者。みんなで汗を流しながら、少しずつ拠点を整えていきました。
大掃除には、5〜10人ほどが参加し、5・6月のうち2日間かけて作業を行いました。その後も、数人ずつが数回にわたって掃除に入り、ようやく、安心して受け入れられる宿泊環境を整えることができました。
正直、ここまでの道のりは簡単ではありませんでした。
空き家探し、交渉、掃除、準備…。一つひとつの作業が地道で、ときには不安にもなりました。
でも、「この町で過ごす時間が、参加者にとって忘れられない体験になってほしい」。その想いは、私だけでなく、関わってくださったみんなが共通して抱いていたものだったと思います。
だからこそ、どんなに大変でも、誰ひとりとして投げ出さずに、最後まで取り組むことができたのだと、今はそう思っています。

ボランティア募集ページの作成
宿泊場所がようやく決まり、掃除や片付けを進めながら、並行して取り組んだのが「募集ページ」の作成でした。
ボランティア生の募集は、ECOFFの公式サイトを通じて行います。全国各地に「〇〇コース」という形で地域ごとのページがあり、川南町も「川南町コース」として掲載することになりました。
しかし川南町は、今回が初めての受け入れ。他の地域では過去の活動写真を使ってページを彩っている一方で、こちらにはまだ何も実績も素材もない、“ゼロからのスタート”でした。
そこで、私だけでなく町内の地域おこし協力隊の方々にも協力をお願いし、川南町の魅力をさまざまな角度から切り取る撮影をスタートしました。
さらに心強かったのは、世話人の一人がプロのデザイナーさんだったこと。写真のセンスも抜群で、この募集ページにおける圧倒的な強みとなってくれました。
どんなページにするか、誰に届けたいのか——。世話人と何度も話し合いを重ね、ターゲットやテーマを丁寧にすり合わせていきました。
そしてたどり着いたのが、
「新しい挑戦の幕開け」
というイメージです。
川南町で初めて世話人が立ち上がり、地域の中からこのプログラムが動き出す——。
その最初の一歩を、写真で表現することにしました。
撮影場所に選んだのは、川南町にあるまっすぐな一本道。その道を背景に、若者たちが楽しそうに笑い合っているシーンを撮影するために、道路使用の許可を取り、何人かの協力者に声をかけ、準備を重ねて臨みました。
完成した一枚は、思わず川南町にこんな素敵な場所があったのか!と驚くような写真になりました。(この写真は募集ページにも使用しているので、ぜひ見てみてください!)
そのほかにも、町の風景や農業の様子、地域の人との交流など、川南町の魅力を写真と言葉にぎゅっと詰め込んで、募集ページがついに完成しました。
そして迎えた募集開始——
わずか1週間で定員5名が埋まり、すぐにキャンセル待ちが出る状況に。
「川南町に行ってみたい」と思ってくれる若者が、こんなにもいる。その事実に、私は改めてこの町の可能性を感じました。
そして、これは自分一人の力では決してできなかったことで多くの方々の力があってこそ、川南町コースに人を呼ぶことができたのだと思いました。
もちろん、これで終わりではありません。これはあくまで始まりの一歩。
受け入れは8月20日から29日までの10日間です。それまでに準備をすることもまだまだあります。
また、冬日程、そして来年の夏・冬と回を重ねていけば、5人、10人、15人と、川南町に足を運んでくれる若者が少しずつ増えていくはずです。
もっと多くの若者に、地方の暮らしの豊かさや、地域の人の温かさに触れ、その良さに気づいてほしい。そして、この町の魅力が未来にちゃんと残っていってほしい。
この「村おこしボランティア」という取り組みを通して、そんな願いが少しずつでも形になっていったらいいなと思っています。
(↓朝5時に世話人と集合し、海から昇る朝日を撮影したときの1枚)

NPO法人ECOFFの皆さまによる現地視察
ボランティア生の受け入れに向けて、6月20日〜21日の2日間、NPO法人ECOFFのスタッフや学生支部の皆さんが川南町へ視察に訪れました。
当日は梅雨とは思えないほどの晴天で、強い日差しのなか、町内の自然や食を楽しんでいただけるよう、さまざまな場所をご案内しました。
ちょうどこの日は「軽トラ市」も開催されており、ECOFFの皆さんは商店街の端から端まで歩きながら、地域の空気を存分に楽しんでいる様子でした。
視察の目的は、ECOFF側と世話人、そして宿泊所となる空き家の所有者との顔合わせと関係構築。懇親会も行い、終始和やかで温かい時間となりました。
ECOFFの方々からは、
「川南町の温かさを感じる場面が多くあった」、「きっととても良いコースになる」、「参加する学生たちも楽しく学べそう」、「また必ず川南に来たい」
といった声があり、たった2日間でも町の魅力をしっかり受け取っていただけたことが私自身も本当に嬉しかったです。
また、世話人からも、
「ちょうどいい距離感で交流できた」、「短い時間だったけど、すごく濃い2日間だった」
といった前向きな声が聞かれ、受け入れ本番に向けてチームの士気を高めることができたような気がしました。
この視察を通じて、他地域の事例や運営の工夫など、川南町コースの設計に生かせるヒントも数多くいただきました。
同時に、宿泊環境や運営体制など、改善すべき点も明確になり、本番に向けてさらに準備を整えていかなくてはと、気が引き締まる思いにもなりました。

大切にしていること
私がこのプログラムで何より大切にしているのは、「自分ではなく、世話人を含めた地域の方々や参加者が主人公になること」です。
参加する大学生にとっては、川南町で出会う人や風景、何気ない日常の中に、将来を考えるきっかけや、自分の価値観を見つめ直す時間があってほしいと願っています。
一方で、受け入れる側の世話人や地域の方々にとっても、若者たちとの関わりの中で刺激を受け、何気ない日々にちょっとした彩りが加わる——そんな時間になれば嬉しいなと思っています。
つまりこの事業は、関わるすべての人にとって“豊かさ”をもたらすものでありたい。川南町で暮らす方々が、若者との出会いをきっかけに、地域の暮らしをもっと楽しむ。
そんなきっかけの一つにもなれるのではと思っています。
「田舎には何もない」と思っていた人が、実は“何もないように見える中にこそ大切なものがある”と気づく——そんな瞬間が、ひとつでも多く生まれてほしいです。
私は、来年の2月末で地域おこし協力隊を退任します。この事業は、私にとって協力隊としての最後で、そして最大の取り組みです。
川南町の未来を思い、自分にできることを考えたとき、「これだ」と心から思えました。
この取り組みが、川南町への小さな贈り物になれたら——。
こんなこといったら恐縮なのですが、でも本当にそんなささやかな願いを込めて、いまこの事業に向き合っています。
地域おこし協力隊としても、町としても、その“はじまり”を支えるにすぎず、
あくまで来年度以降は世話人方が自走していく形を目指していますが、退任後も微力ながらいち地域住民としてこの事業に関われたらと思っています。
受け入れ日程まであと約1か月。
受け入れ時の様子などは、広報かわみなみやこのブログなどでまた報告します!今後も応援していただけたら嬉しいです!